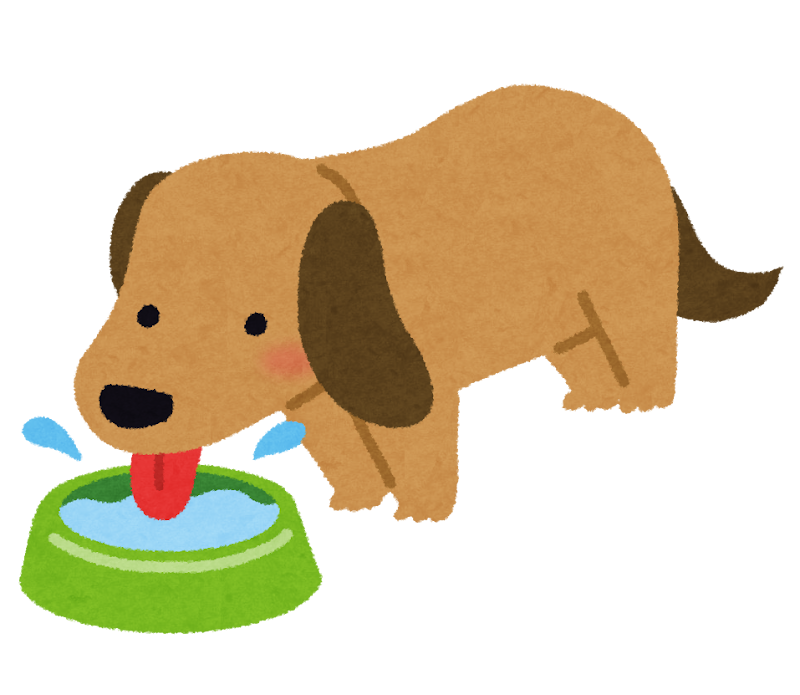
犬がいつもより水をよく飲む、尿の量が増えた――
そんな変化は、腎臓病を含むさまざまな病気のサインかもしれません。
とくに慢性腎臓病は、気づきにくいまま進行することがあるため注意が必要です。
腎臓病の重症度を判断する基準として使われているのが「IRIS分類」。
この記事では、
・犬が多飲多尿になる主な原因
・IRIS分類の見方
・ステージごとの治療のポイント
を、多飲多尿で来院した雑種犬の虎徹くんの例を挙げて、
獣医師の視点から分かりやすく解説します。
症例
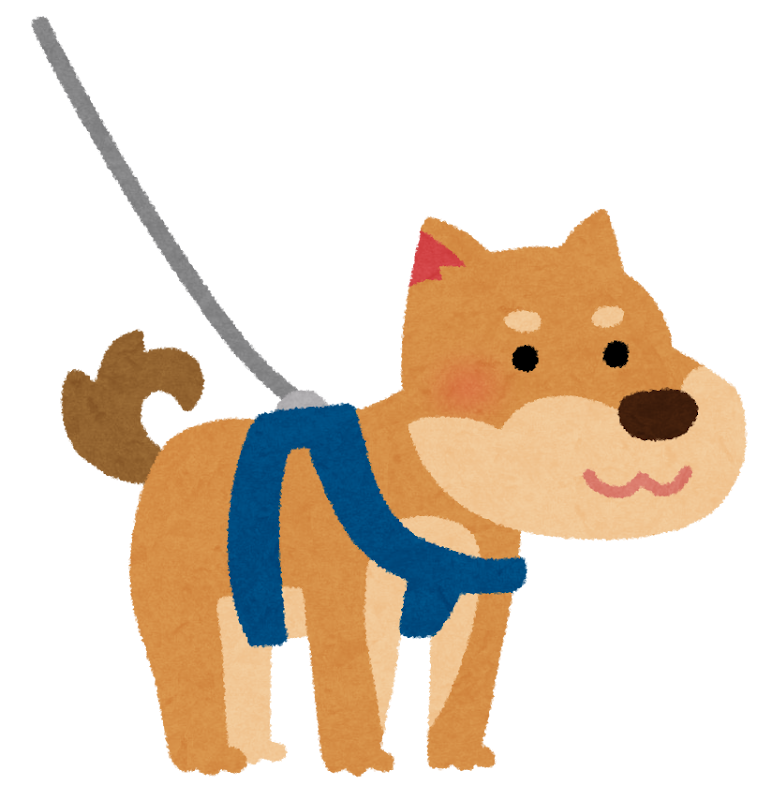
13歳、雑種、虎徹くん。甲状腺機能低下症で治療中。
今日は再診がてら、相談があるとのこと。

暑くなってから、ガブガブとものすごく水を飲みます。
おしっこも家の中でしないので夜中に鳴いて起こすんですよ・・
間に合わないこともあります。
元気も食欲もあるんですけどね〜
多飲多尿について
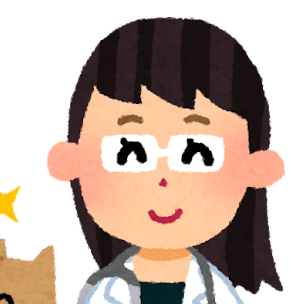
大体で良いのですが、1日にどのくらい飲んでいるかわかりますか?

500mlちょい入る水皿があっという間になくなるのでおかわりして、
散歩中にも飲んでるから・・・3L近くは飲んでます。
虎徹くんは、体重20kgくらいなので、1日の飲水量の基準量は、1Lくらいです。
3L位は明らかに、多飲です。
✅ 犬・猫の「多飲多尿」の基準
犬・猫の飲水量は、個体差・季節・食事(ドライかウェットか)などでも変動します。
以下の飲水量の基準と合わせて、本当に異常な多飲なのか?考えます。
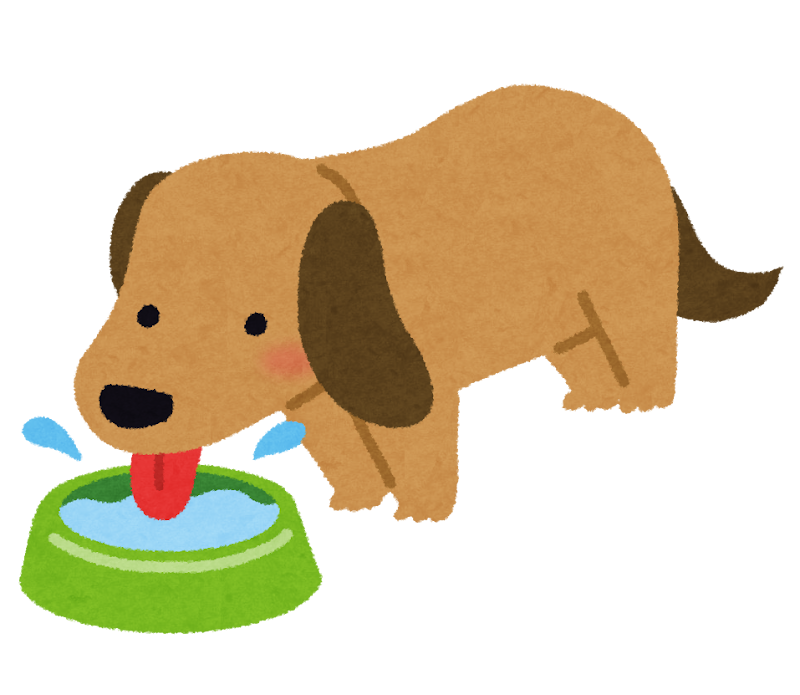
| 種類 | 多飲の基準(1日の飲水量) | 正常な飲水量 |
|---|---|---|
| 犬🐶 | 体重1kgあたり 100mL以上 | 体重1kgあたり50〜60ml |
| 猫🐱 | 体重1kgあたり 45mL以上 | 体重1kgあたり 40〜50mL |
⚠️数日〜1週間以上、多飲が続く場合は病気のサインです。
多飲多尿の原因

多飲多尿の原因は、以下のように、とってもたくさんあります!
病的なのか、病的でないのか(気温、環境の変化やストレスなど)?
がとても大切です。
| カテゴリー | 主な病名・原因 | 補足 |
|---|---|---|
| 代謝性 | 糖尿病・高カルシウム血症 | 血糖/カルシウムの上昇で尿量増加 |
| 腎臓 | 慢性腎臓病・腎性尿崩症 | 腎臓で尿を濃縮できない |
| 内分泌 | クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)・中枢性尿崩症 | ホルモン異常で尿量が増える |
| 感染症 | 子宮蓄膿症・腎盂腎炎 | 発熱や炎症性で多飲に |
| 肝臓 | 肝不全・門脈体循環シャント | 代謝異常で多飲多尿になる |
| 薬剤性 | ステロイド・利尿剤 | 利尿作用のある薬による |
| その他 | 心理性多飲症 | 環境・ストレスが原因になる |
検査:多飲多尿の原因は?
尿検査
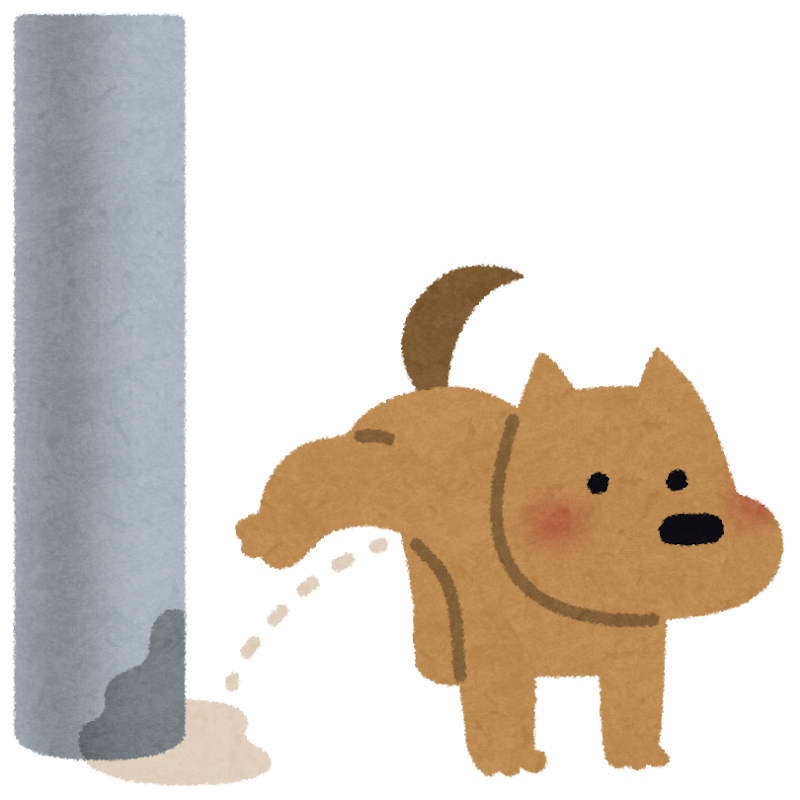
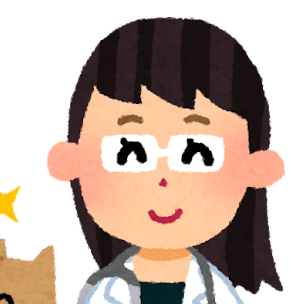
多飲多尿の鑑別には尿検査が不可欠です。
尿比重・尿糖・尿タンパク・沈渣などから、
腎臓病、糖尿病、尿崩症、膀胱炎、ホルモン異常などの原因を、絞ることができるためです。
【虎徹くんの尿検査】
- 尿糖(ー)
➡️ 糖尿病は否定的 - 炎症細胞・細菌(ー)
➡️ 腎炎・膀胱炎は否定的 - 尿比重:低下↓
➡️ 多飲による希釈尿、あるいは腎機能低下
血液検査🩸
血液検査も、多飲多尿の原因を大きく絞り込むために重要な検査です。
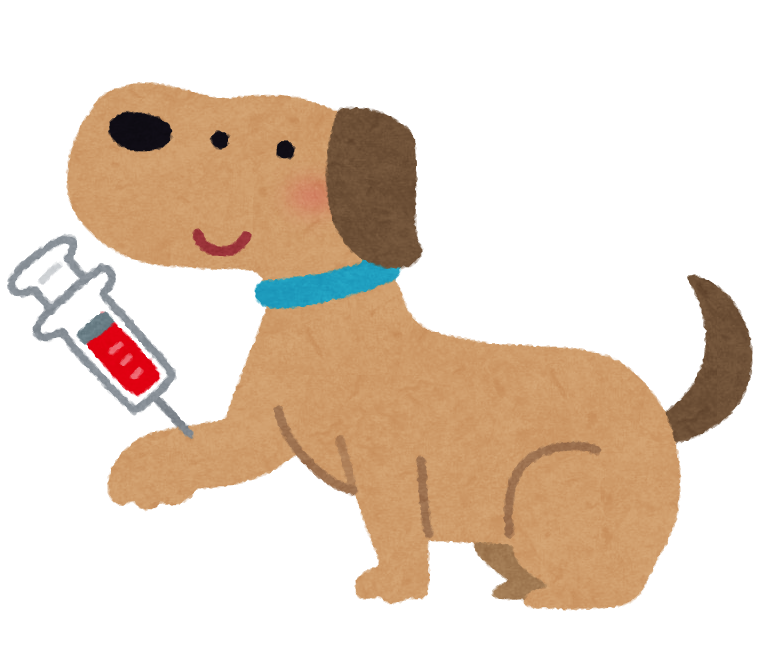
【虎徹くんの血液検査】
BUN:36mg/dL(7〜27 mg/dL)
クレアチニン:1.4mg/dL(0.5〜1.4 mg/dL)
SDMA :20mg/dL(0〜14 µg/dL)
※( )内は正常値
腎機能の評価項目が、それぞれ基準値の上限のぎりぎりか、少し上回っていました。
その他の項目に異常はありませんでした。
超音波検査

血液検査や尿検査で異常が見つかった場合、超音波検査で臓器の形態的異常を確認することで、
多飲多尿の原因を特定しやすくなります。
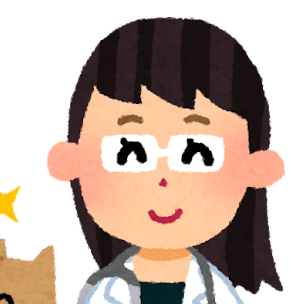
これまでの検査で、尿比重の低下や、血液検査で腎臓の数値がやや高かったことから、腎臓の確認を目的に超音波検査を行います。
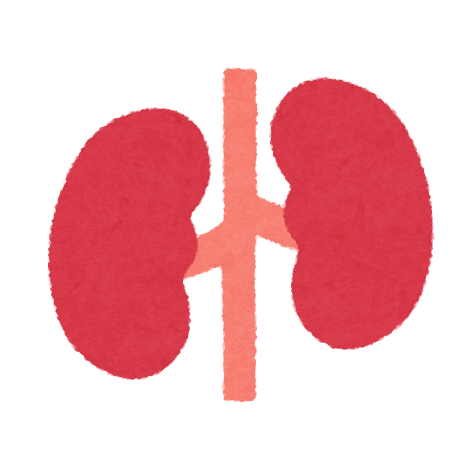
虎徹ちゃんの腎臓には、萎縮や腫大、腎結石などの明らかな異常は見つかりませんでした。
しかし、尿量が増えているため、腎臓の中心にある腎盂がわずかに拡張し、
腎臓の構造がやや不明瞭になっていました。
結果:初期の腎機能低下
【 初期の腎機能低下 】
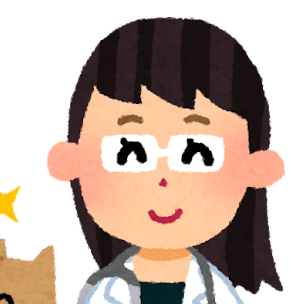
以上の検査から、虎徹ちゃんは、初期の腎機能低下の可能性があります。
IRIS(アイリス)のステージは1〜2ですが、多飲多尿が顕著なので、本人も少し辛い状況だと思います。治療を検討してみましょうか。
犬の腎障害について
IRIS(International Renal Interest Society、アイリス)分類 は、
慢性腎臓病(CKD)の重症度を客観的に評価するための国際基準です。
🐶 腎臓病のIRIS分類
| ステージ | 血清クレアチニン (sCr) | SDMA | 簡単な説明 |
|---|---|---|---|
| Stage 1 | < 1.4 mg/dL | 正常〜軽度上昇 | 腎臓に何らかの異常が疑われるが、まだ明らかな高窒素血症はなし。 |
| Stage 2 | 1.4 – 2.0 mg/dL | 軽度上昇 | 軽い腎機能低下。症状はほとんど出ないことが多い。 |
| Stage 3 | 2.1 – 5.0 mg/dL | 中等度上昇 | 中等度の腎機能低下。脱水、食欲低下、体重減少などの症状が出やすい。 |
| Stage 4 | > 5.0 mg/dL | 高値 | 重度の腎不全。積極的な治療や管理が必要。 |
※注記
この表は、IRIS の 2023 年版の CKD ステージ分類/治療ガイドラインに準拠しています。
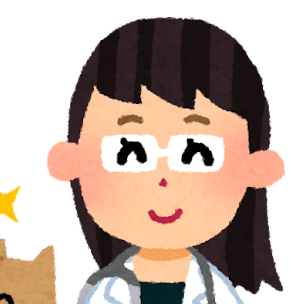
ステージ判定には血清クレアチニン/SDMAだけでなく、尿たんぱく(UPC)・血圧・尿比重・臨床症状などもあわせて評価するのが基本です。
🐶 CKD(慢性腎臓病)IRISステージごとの治療の目安
IRISのステージを目安に、治療を検討していきます。✏️
| ステージ | 目標・方針 | 具体的な管理ポイント |
|---|---|---|
| Stage 1 | 腎臓の変化を早く見つける | – 定期検査(血液・尿・血圧)- 可逆性要因の除去- 療法食は症状や検査で獣医と相談 |
| Stage 2 | 進行の抑制 | – 療法食を検討- 水分補給・生活環境の見直し- 血圧・尿たんぱくのチェック |
| Stage 3 | 症状や合併症への対応 | – 療法食必須(リン制限など)- 水分補給・脱水対策- 血圧・電解質・尿たんぱくの管理 |
| Stage 4 | QOL維持・支持療法 | – 療法食必須- 水分補給や補液- 合併症管理(高血圧、貧血など)- 食欲不振時は補助療法も |
※注記
この表は、IRIS の 2023 年版の CKD ステージ分類/治療ガイドラインに準拠しています。
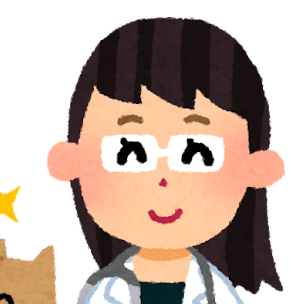
療法食の導入は「犬の体調、食欲、好み、他の検査値」もふまえて、担当の獣医師と相談してくださいね!
🔍 治療のポイント
- 早期ステージほど 生活管理や食事療法が中心になります。
- 進行ステージほど 薬物療法・輸液・合併症管理が重要です。
- 定期的な血液・尿検査で ステージの進行を把握 することが治療の基本になります。
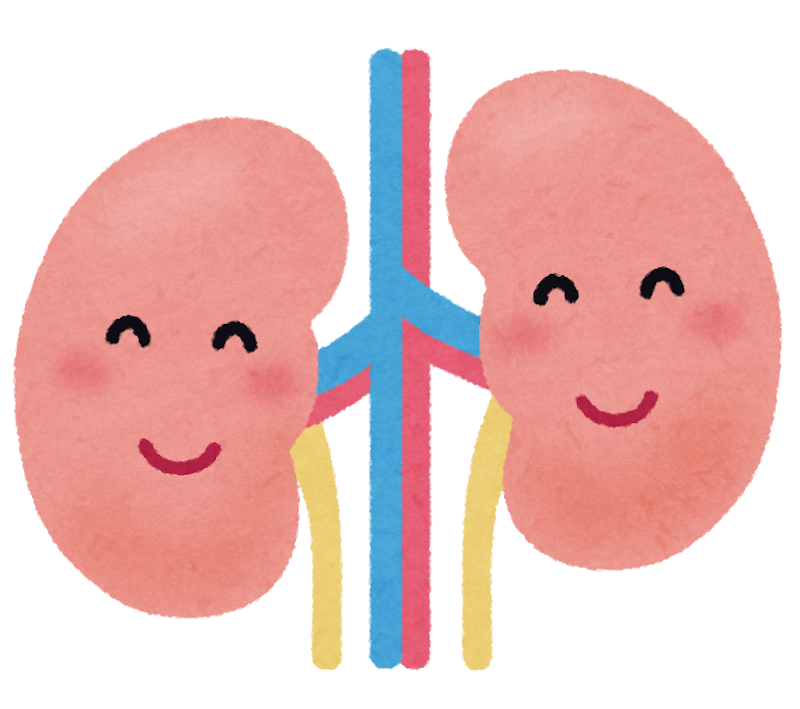
治療:腎臓の療法食からスタート

腎臓の療法食の特徴🍽️
腎臓の療法食は、いろいろなメーカーが製造しています。
主に以下のような特徴があり、腎臓の障害の進行を遅らせたり、症状を緩和させたりします。
1. タンパク質の調整
- 腎臓に負担をかけない 高品質・適量のタンパク質
- 老廃物(尿素・クレアチニン)の生成を抑える
2. リンの制限
- 腎機能が低下するとリンが体内に蓄積しやすい
- リンの量を調整することで、腎不全の進行を遅らせる
3. エネルギーの調整
- タンパク質が制限されても十分なカロリーを確保
- 食欲低下時でも必要な栄養を摂取しやすい
🐶動物病院でも紹介している、腎臓の療法食の例です。⬇️
その後・・・
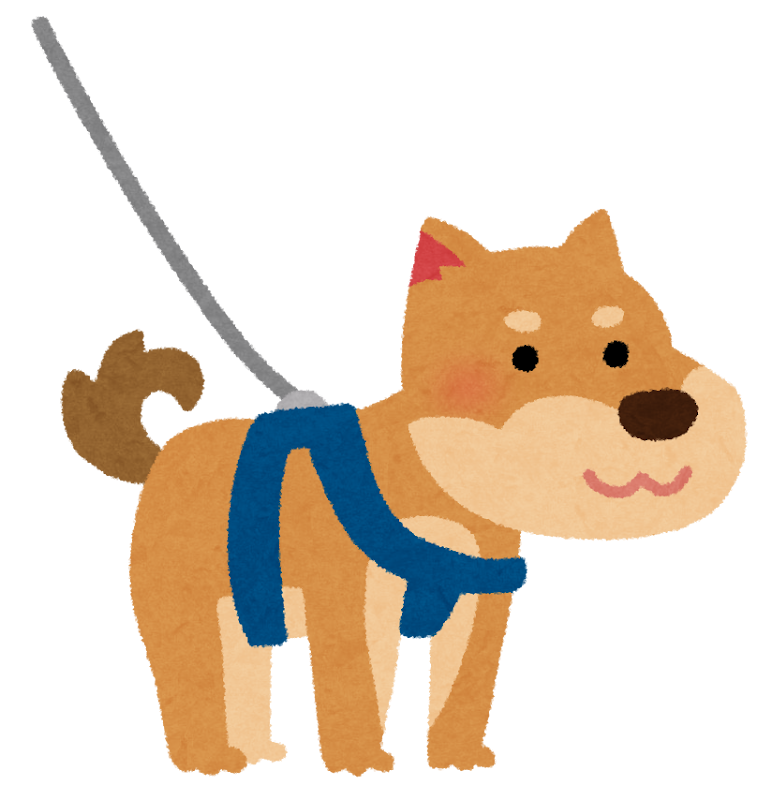
虎徹ちゃんは、食事療法から始めて、多飲多尿の症状が落ちついてきたとのこと。

腎臓の療法食にしてから、飲水量は1日に1Lくらいに落ち着きました。
おしっこも量が減って、夜中におしっこに起こされることがなくなりました。
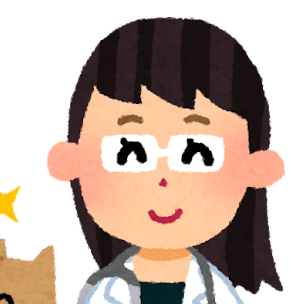
よかったです!
このまま、元気・食欲などに問題なければ、食事の療法食を続けて、
3ヶ月くらいで定期検診で血液検査や尿検査にいらしてください!
まとめ
犬の多飲多尿は、原因がかなりたくさんあります。
環境の変化(新しい犬がお家に来た、大好きなお母さんが不在だったなども)や、運動量、気温、ご飯の変更も、多飲多尿の原因になります。
しかし、今回の腎機能低下の他、膀胱炎、糖尿病、クッシング症候群、悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症など・・・怖い病気が隠れている可能性もあります。

腎臓の機能低下の初期症状は、多飲多尿がみられることがあります。
治療はIRIS(アイリス)分類に基づきステージに応じて提案してきます。
初期であれば、腎臓の療法食が病気を遅らせるのに有効です。
もし、犬に多飲多尿が見られたら、だいたい、どのくらい飲んでいるのか確認して、できれば尿を持参して、動物病院に相談してみてくださいね!
今回の、多飲多尿の虎徹くんの1例、参考にしていただけましたら幸いです。
※本記事は、獣医師としての臨床現場での経験に基づいてまとめています。
個々の動物によって症状は異なりますので、気になる場合は動物病院での診察をおすすめします。
参考文献
- IRIS. IRIS Staging of Chronic Kidney Disease. International Renal Interest Society.
- Ettinger SJ, Feldman EC, Côté E. Textbook of Veterinary Internal Medicine. Elsevier.
- Polzin DJ. Chronic Kidney Disease in Dogs and Cats. Vet Clin North Am Small Anim Pract.

コメントやご相談もお待ちしています!



コメント