猫が、トイレに行ったり来たり。
膀胱炎かな?もしかして、おしっこ出てない?
膀胱炎のための頻尿なのか、尿道が詰まって出てこないのか。
ぱっと見には判断が難しいです。
場合によっては、緊急事態になることもあります。
動物病院では、どんなことををするのか?採尿はどうするのか?
今回は、何度もトイレに行く猫のトムくんの例を紹介し、膀胱炎の原因、採尿方法や治療についてまとめました。

症例
猫のトムくんは、5歳の男の子。

昨日から、何度もトイレに行ったり来たりしています。
おしっこの姿勢をするけど、ほんのちょっとしか出ていないみたい・・・

診察🚽:頻尿 or 閉塞?
猫、特に雄猫が、何度もトイレにいくとき、
おしっこを膀胱に溜めておけない(痛いので)、【頻尿】なのか?
おしっこを出すことが出来ない、【尿道の閉塞】なのか。
外見からは判断がつきにくいです。
すぐにお腹を触って、膀胱の状態を確認します。
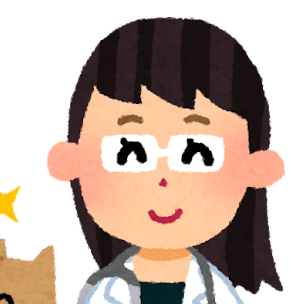
おしっこは、ほとんど溜まってないようですね。
トムくんの場合は、膀胱炎で頻尿になっている可能性が高いです。
頻尿とは?
- 何度もトイレに行く
- 1回の量が少ない
- 砂をかく時間が長い
→ 痛みや違和感があるときのサイン です。
多くは 膀胱炎(ストレス性のことが多い)で、命に関わらないことが多いです。
ただし 油断すると悪化して詰まる→尿道閉塞 に進むことがあります。
尿道閉塞とは?
オス猫は尿道が とても細く、特に先端は 直径1mmほど しかありません。
そこに 結晶・砂・炎症の粘りが詰まる → 尿が出なくなる状態。
尿が出ない → 体の中に毒がたまる(尿毒症)
そのままだと 半日〜1日で命の危険 があります。
検査
超音波検査
膀胱の状態を確認します。
膀胱の壁が厚くなって、おしっこは濁ってモヤモヤしています。
膀胱内に結石はありませんでした。

尿検査

トムのおしっこ、取ってこれませんでした。検査できませんか?
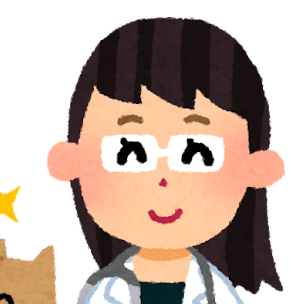
大丈夫です!動物病院ですぐ採尿できますよ。
動物病院では、尿道カテーテルを入れて採尿したり、
超音波ガイドでお腹から注射の針を刺して直接膀胱から採尿します。
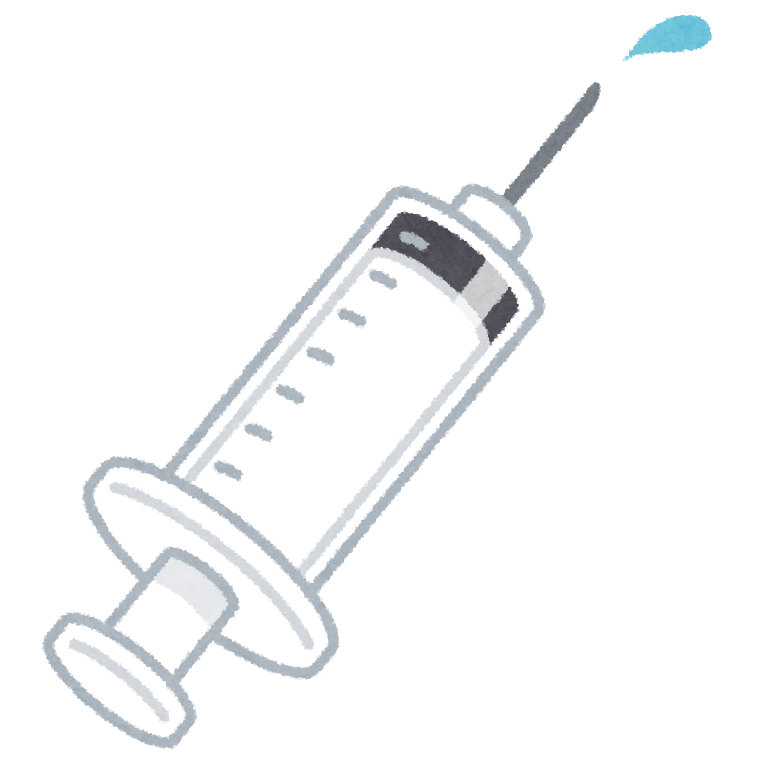
トムくんは、尿道カテーテルでおしっこをとることが出来ました。
お家でおしっこを取る方法🐱
自宅でおしっこをとることができれば、動物病院での尿検査がスムーズです。
また、動物病院で怖がりでじっと出来ない子で採尿が難しくても、安全に尿検査を行うことができます。
普段のトイレがペットシートなら
ペットシートの裏面のビニールの部分を上に向けておくと、猫がそのままおしっこをするとビニールに尿が溜まるので、尿を取ることができます。
猫砂(固まるタイプ)なら
猫砂を片付けて、そこに尿をしたら、回収します。
猫が、あれっ猫砂ない??と動揺して、トイレをためらう場合もあります・・・
システムトイレなら
システムトイレは、尿がサンドを通過して下に落ちる仕組みになっています。
下のシートを敷かなければ尿が溜まるので、回収が簡単です。
猫のおしっこトラブルは割と多いので、すぐに採尿準備ができるシステムトイレはお勧めです。⬇️
尿を持ってくる方法🫙
集めた尿は、清潔な入れ物に入れてください。
動物病院にあらかじめ相談するとシリンジなどを渡してくれると思います。
なるべく早く、半日以内に動物病院に持参しましょう。
2時間以上かかるようなら、冷蔵庫に入れて保存してください。
尿検査についてはこちらも参考にしてください🐱⬇️
尿検査:膀胱炎の原因は?
トムくんの尿検査の結果・・・尿中に、炎症の細胞と、細菌が確認されました。
細菌性膀胱炎として、治療することになりました。
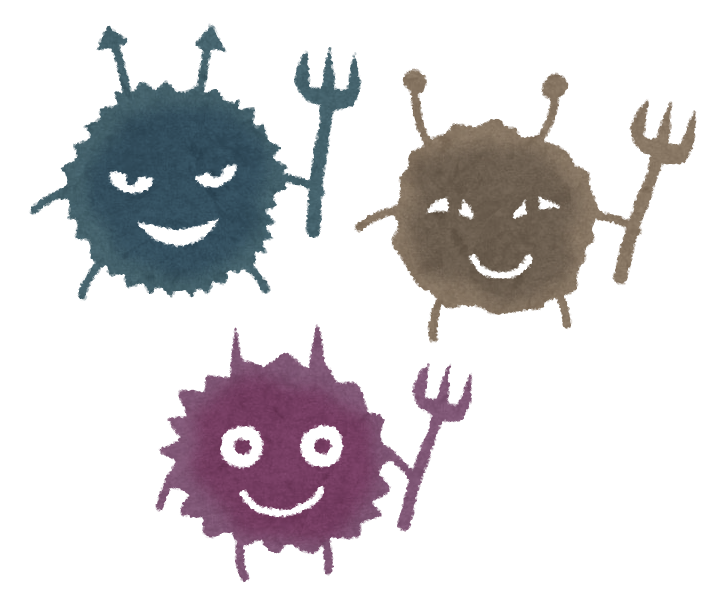
猫の膀胱炎の原因は
- 特発性膀胱炎🩸
- 細菌感染🦠
- 尿石・結晶💎
などが挙げられます。それぞれ治療法が違うので、尿検査はとても大切です。
その他の膀胱炎についてはこちらの記事も参考にしてください🐱⬇️
治療
細菌性膀胱炎の治療は、約2週間程度、抗菌薬💊を続ける必要があります。
症状がなくなっても途中でやめてしまうと、再発のリスクがあります。

トム、薬んだことありません💦
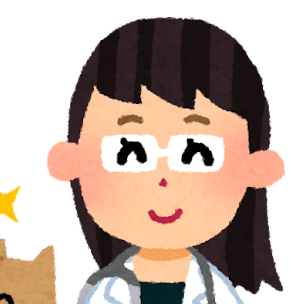
今回は、2週間持続して効果がある抗菌薬の注射をしましょう。
痛み止めの注射も一緒にしていきますね!

落ち着いていれば、1週間後、尿検査で菌がいなくなっているか確認します。
投薬について
猫はお薬を飲ませるのに苦労することが多いです。
動物病院では、持続する抗菌薬の注射など便利なものもありますが、この抗菌薬が効かなかった場合や、抗菌薬以外のもので治療する場合は、どうしても飲み薬が必要なことが多いです。
動物病院では、実際に投薬指導を行なってますが、以下のようなものを使うと、おやつ感覚でうまく行くかもしれません!
ペースト状のおやつに混ぜて投薬するタイプです💊⬇️
お薬を包んで投薬するタイプです💊⬇️
その後
その後、頻尿もすぐにおさまり、平穏な日常に戻ることができたとのことです。
1週間後の尿検査では、炎症細胞や細菌は確認されませんでした。

採尿もスムーズに出来ました!検査でも問題なくなってよかったです!
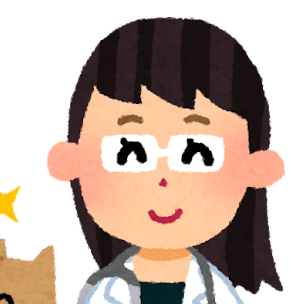
念の為、1ヶ月後くらいに再度尿検査をして、問題なければ治療は終了です!

まとめ
猫は膀胱炎や尿石症など、おしっこトラブルの多い動物です。
急にトイレに行ったり来たりしている場合、
頻尿であれば、猫はとても辛い状態。尿道閉塞であれば緊急事態です。
なるべく早く動物病院に連れて行ってあげてください。
また、おしっこを持参できたら、検査がとてもスムーズです。
再検査では、猫が病院に行かなくても尿の確認ができるので、自宅で採尿できるように、ぜひ備えておくことをお勧めします。

細菌性膀胱炎の猫のトムくんの一例、参考にしていただけましたら幸いです!
※本記事は、獣医師としての臨床現場での経験に基づいてまとめています。
個々の動物によって症状は異なりますので、気になる場合は動物病院での診察をおすすめします。
参考文献
・Weese JS et al. (2019) ISCAIDガイドライン
・Sparkes AH et al. (2016) ISFM膀胱炎ガイドライン
・Little SE. The Cat: Clinical Medicine and Management. 2015


コメントやご相談もおまちしています。

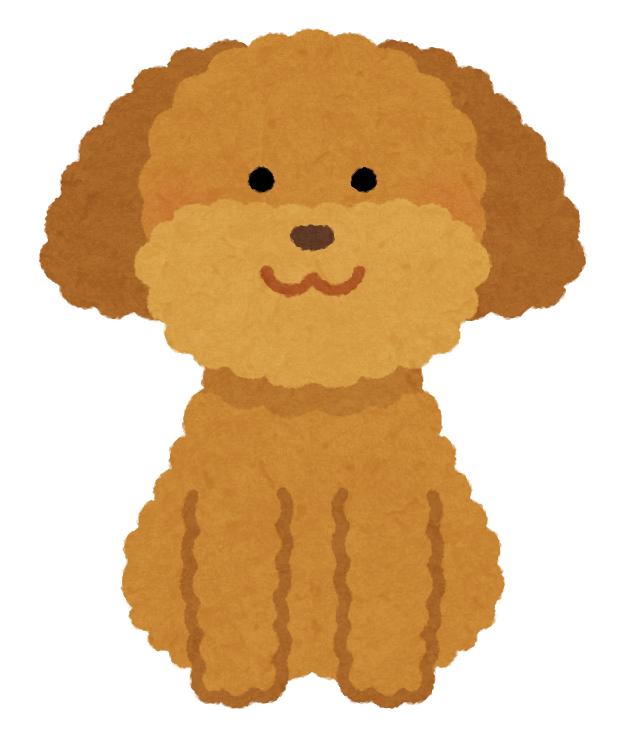

コメント