猫は泌尿器系のトラブルがとても多い動物で、膀胱炎・結石・腎不全など様々な病気が見つかることがあります。
その中でも 尿検査は、猫の健康状態を知るうえでとても重要な検査 です。

おしっこには、体調のヒントがたくさん隠れています。
採尿はカテーテルや膀胱穿刺で病院でもできますが、
自宅で採尿ができれば、猫に負担をかけず、診断もスムーズになります。
さらに猫は体調不良を隠しやすい動物。
いつでも採尿できる準備をしておくことは、愛猫の健康を守る大きな助けになります。
この記事では、猫の尿検査でわかる病気 と 自宅でできる採尿方法 をわかりやすくまとめました。
🐱猫が病気の時、おしっこはどうなる?🚽
猫に多い、尿検査で見つかる病気をピックアップしてみました。
膀胱炎🔥

細菌性膀胱炎と、猫で最も多い突発性膀胱炎。
尿検査をしないと見分けがつきません。
治療も違うので、尿検査はとっても大切です!
尿はどうなる?
細菌性 ➡️ 細菌、炎症細胞。血液や、ストルバイト結晶が見つかることも。
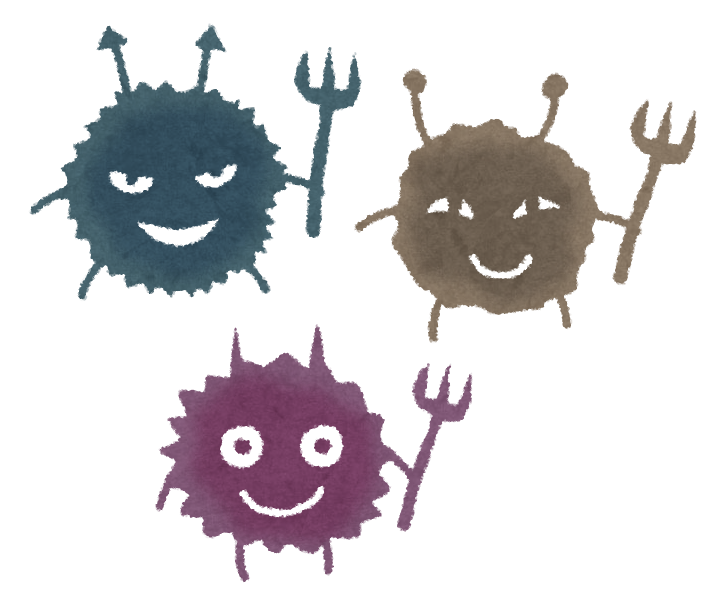
突発性 ➡️ 血液成分のみ。細菌、炎症細胞なし。

膀胱結石🪨
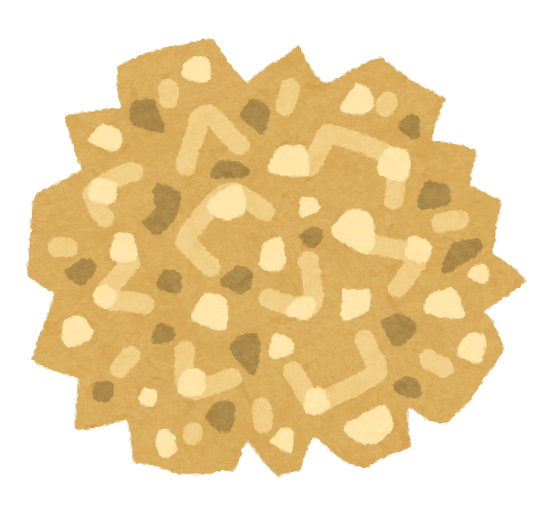
猫では尿路結石は比較的よく見られる病気で、細菌感染・食事・体質などが原因となってできます。
無症状のまま進行してしまうことも多いため、健康診断としての尿検査はとても重要です。
定期的な尿検査で偶然みつかり、早めに治療を始められるケースも少なくありません。
尿はどうなる?
ストルバイト結晶や、シュウ酸カルシウム結晶などが確認されます。
尿のp Hが酸性やアルカリ性に傾きます。
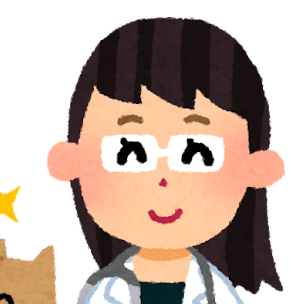
肉眼で尿を見て、なんだかキラキラしている・・・と、尿中の結晶に気づくこともあります。
糖尿病🍰

猫では肥満に関連して糖尿病になる子もいれば、膵炎に続いて糖尿病になる子もいます。
尿はどうなる?
尿糖が陽性になります。これと、高血糖が確認されれば、糖尿病の可能性が高いです。

腎機能低下
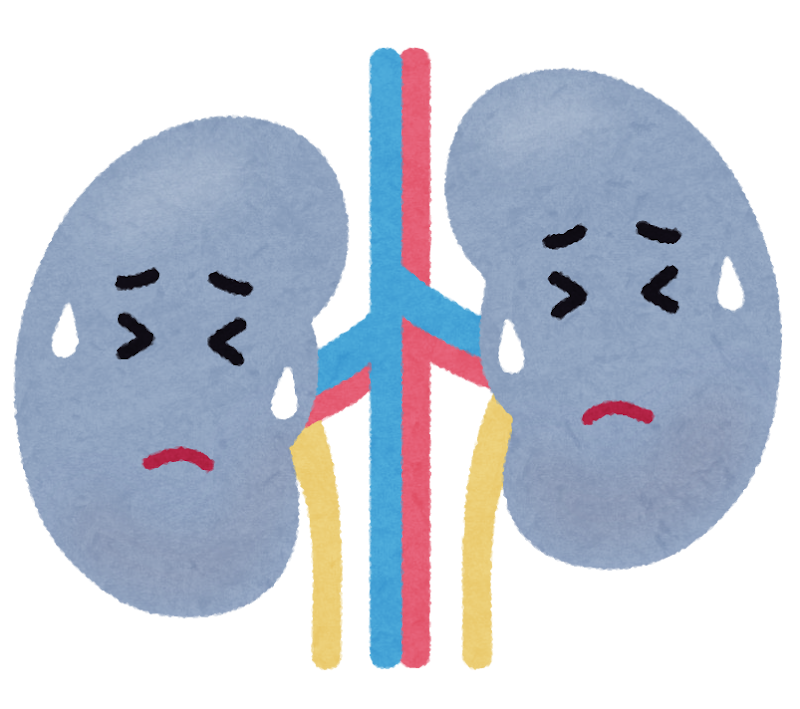
腎臓の機能低下が起こると、尿を濃くすることができなる結果、水に近いような尿になります。
尿はどうなる?
薄く、透明に近くなります。おしっこのが増えます。尿蛋白が出ることもあります。

肝臓疾患(黄疸)
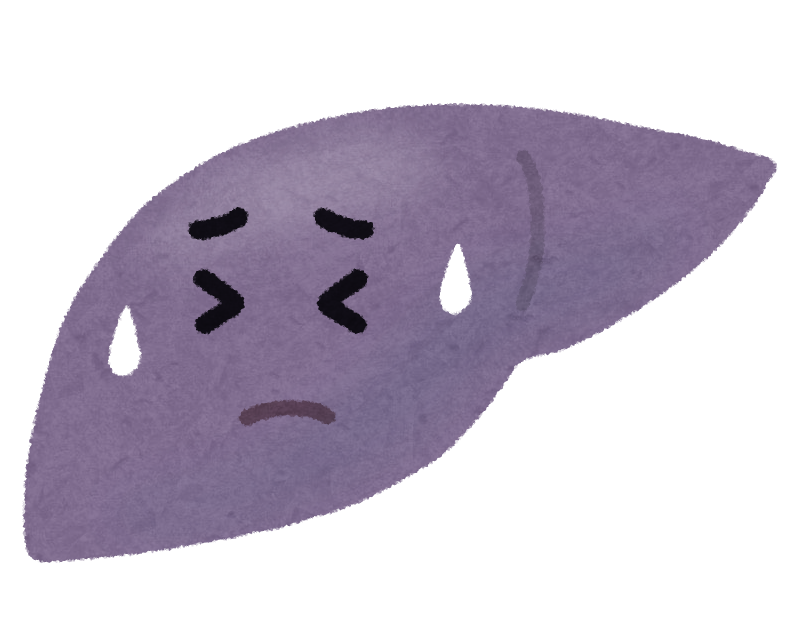
猫が黄疸を示す原因となる病気はさまざまです。
肝炎、胆嚢炎、肝臓腫瘍、脂肪肝などが代表的です。
黄疸は皮膚が黄色くなる症状ですが、猫は全身が被毛に覆われているため、外見からはとても気づきにくいのが特徴です。
尿はどうなる?

おしっこがとても濃い色、オレンジジュースのような色になります。
潜血ではなく、ビリルビンが陽性になります。
🐱どうやって、尿をとる?
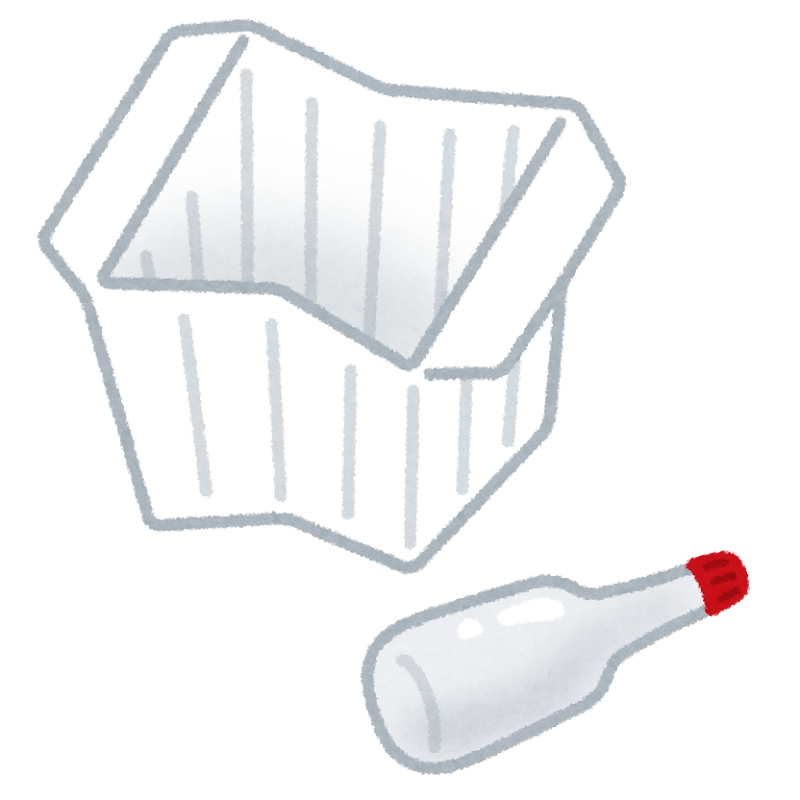
尿を持参すると、検査がとてもスムーズになります。
ペットシーツの場合

普段ペットシーツであれば、ペットシーツのビニール面を上にしておけば、猫がそのままおしっこをすると、尿が吸収されず溜まります。これを採尿しましょう。
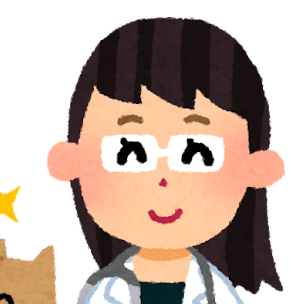
⚠️便がついてしまうと、尿に細菌が混じってしまうので注意しましょう。
採尿に便利なシステムトイレ🚽✨
上段の「スノコ」と下段の「トレー」からなる2層構造のシステムトイレであれば、下段に尿が落ちるので、下の吸収材を外しておけば、そのまま尿が下に溜まります。
採尿がとても簡単で、おすすめです✌️⬇️
猫の健康管理もできる!モニター型トイレ🚽✨
さらに進化した、猫トイレも!毎日の健康管理がスマホでできる、すごいシステムです👇
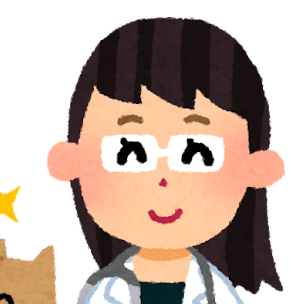
なるべく新鮮な尿を取れるとより良いです!
ベストは採取から1〜2時間以内、最大で4時間以内が理想的です!
量は❓

10ccくらいあるととても良いです⭕️
それ以下でも検査ができることがあるので、取れたら持参しましょう。
容器は❓🫙
洗って乾かしたジャム瓶など、清潔なものを使いましょう。
動物病院にあらかじめ相談すると、シリンジなどを渡してくれると思います。
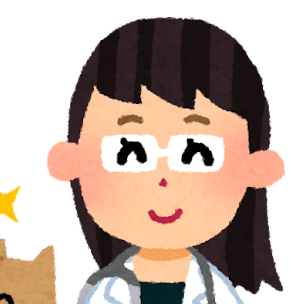
❌猫砂や、ペットシーツに染みてしまうと、尿検査できません💦
🐱まとめ🚽
猫は泌尿器の病気がとても多く、おしっこの状態から体調の変化に気づけることがよくあります。
しかし、猫は体調不良を隠しがちな動物。だからこそ、早めの気づきがとても大切です。
膀胱炎や膀胱結石の再検査、健康診断としての尿検査は、自宅で採尿できれば通院せずに確認することも可能です。
そのため、猫の体調管理には尿検査がとても重要。
「いつでも採尿して検査に出せる」ように準備しておくことは、愛猫の健康を守る大きな助けになります🐱
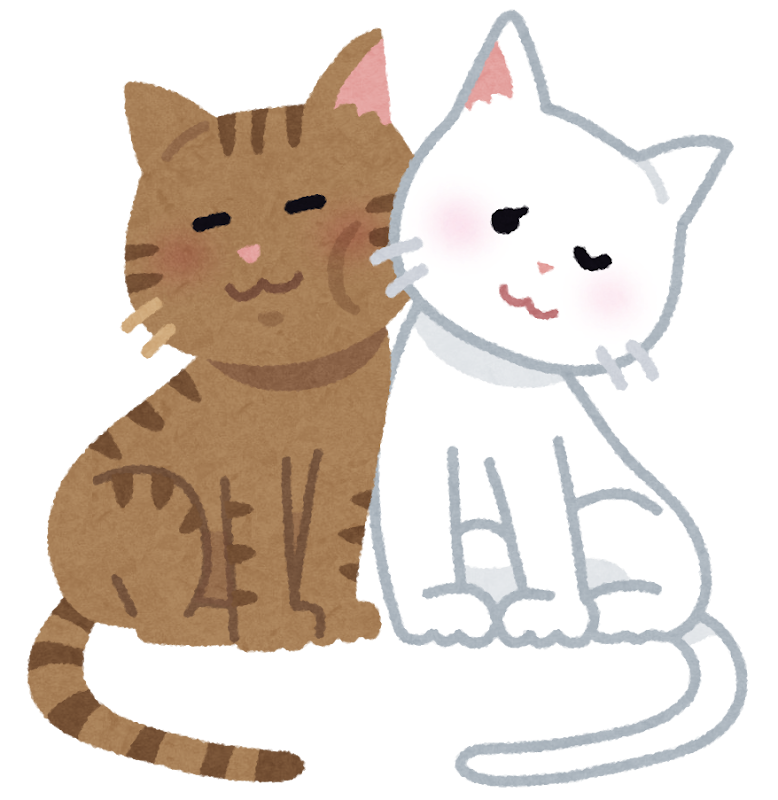


※本記事は、獣医師としての臨床現場での経験に基づいてまとめています。
個々の動物によって症状は異なりますので、気になる場合は動物病院での診察をおすすめします。
参考文献
Ettinger SJ, Feldman EC, Côté E (eds). Textbook of Veterinary Internal Medicine, 8th ed.
Bartges J, Polzin DJ. Nephrology and Urology of Small Animals. Wiley-Blackwell.
Grauer GF. Urinalysis in the Diagnosis of Renal Disease. Vet Clin North Am Small Anim Pract.
コメントやご相談もお待ちしています!
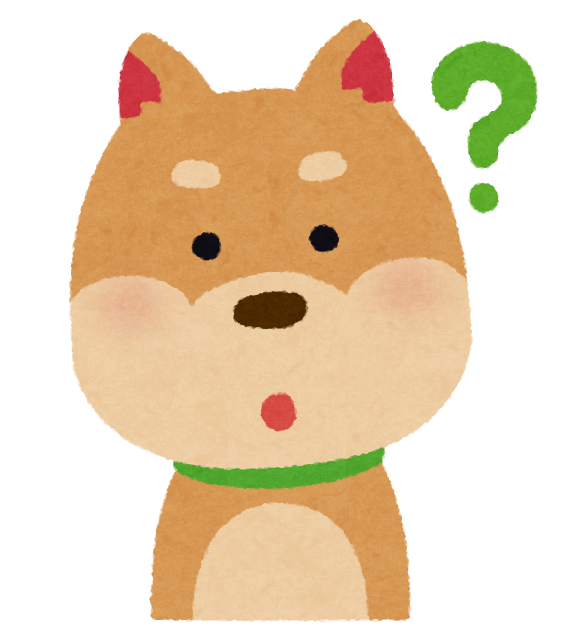

コメント